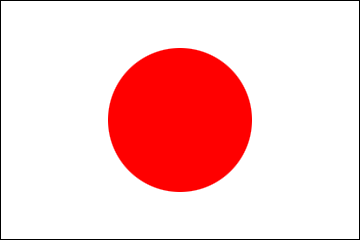日本の対モンゴル政府開発援助(ODA)
令和5年12月28日
1. 変遷と実績
日本政府によるモンゴルに対するODAは1977年に締結された経済協力協定に基づき実施された無償資金協力「ゴビ・カシミヤ工場建設」に始まりますが、1989年度までは研修員の受入、専門家派遣、機材供与を中心とした技術協力および文化無償資金協力といった限られた分野に留まっていました。その後、1990年にモンゴルが社会主義体制から市場経済体制に移行したことを機に日本による一般無償資金協力が再開されるとともに円借款が初めて供与され、日本の対モンゴルODAは本格化します。
無償資金協力では、民主化直後、国際機関も含めた他ドナーと協調を図りつつ、インフラ分野(発電所、通信、運輸関連)、農畜産分野(食肉加工施設、乳製品加工施設、穀物貯蔵施設、食糧支援、農業資機材の供与など)への支援を実施し、市場経済移行期のモンゴル国民の生活を支えました。その後は初等・中等学校の建設(59校、729教室)、保健医療機材の供与、消防車両・ゴミ収集車等の防災・衛生車両の供与、日本モンゴル教育病院建設計画などが実施され、市民生活に必要なインフラ整備が行われてきました。また1990年に開始した草の根無償資金協力では、主として地方の学校や病院の改修など、地方の草の根レベルのニーズに応える支援を全ての県で実施しており、2022年11月末現在の支援総数は596案件に達しています。近年では、首都ウランバートルへの急速な人口の一極集中に伴って大気汚染などの環境問題や年々深刻化している交通渋滞など、都市問題も顕在化しているため、2010年から「大気汚染対策能力強化プロジェクト」を継続的に実施(現在フェーズ3)し、大気汚染に関する測定技術の強化や日本の環境対策・制度などについての技術指導も行っています。また、2012年には「ウランバートル市高架橋(通称:太陽橋)」を建設し、交通渋滞の緩和、経済活性化及び社会サービスへのアクセスの向上を図っています。
有償資金協力では、低利で返済期間の緩やかな条件を活かして、モンゴル国内の炭坑施設の改修およびスペアパーツ供与、火力発電所の継続的な改修、新空港の建設など大規模なインフラ整備事業を中心に様々な経済援助を実施してきました。また鉱業依存の経済体制を改善し、民間セクター主導による産業の多様化を図るため、モンゴルの中小企業に対する低金利・長期の融資を行うための円借款「中小企業育成・環境保全ツーステップローン」を2005年と2010年の2回に渡り総額80億円供与しました。更に最近では、モンゴルが必要とする産業人材を育成し、同国の工学系高等教育機関の機能を強化するために、有償資金協力によって「工学系高等教育支援計画(MJEED)」を実施し、日本への留学を通じた人材育成への支援を行っています。
このように日本政府は、モンゴルとの外交関係樹立から今日まで様々な分野での支援を実施しており、2021年度までの支援総額はおよそ3641.07億円に達しています。このような日本政府のモンゴルに対する一貫した支援により、民主化への移行期という財政的に最も苦しい時期に極めて大きな役割を果たすとともに、モンゴルの国造りを担う人材育成を行っています。
無償資金協力では、民主化直後、国際機関も含めた他ドナーと協調を図りつつ、インフラ分野(発電所、通信、運輸関連)、農畜産分野(食肉加工施設、乳製品加工施設、穀物貯蔵施設、食糧支援、農業資機材の供与など)への支援を実施し、市場経済移行期のモンゴル国民の生活を支えました。その後は初等・中等学校の建設(59校、729教室)、保健医療機材の供与、消防車両・ゴミ収集車等の防災・衛生車両の供与、日本モンゴル教育病院建設計画などが実施され、市民生活に必要なインフラ整備が行われてきました。また1990年に開始した草の根無償資金協力では、主として地方の学校や病院の改修など、地方の草の根レベルのニーズに応える支援を全ての県で実施しており、2022年11月末現在の支援総数は596案件に達しています。近年では、首都ウランバートルへの急速な人口の一極集中に伴って大気汚染などの環境問題や年々深刻化している交通渋滞など、都市問題も顕在化しているため、2010年から「大気汚染対策能力強化プロジェクト」を継続的に実施(現在フェーズ3)し、大気汚染に関する測定技術の強化や日本の環境対策・制度などについての技術指導も行っています。また、2012年には「ウランバートル市高架橋(通称:太陽橋)」を建設し、交通渋滞の緩和、経済活性化及び社会サービスへのアクセスの向上を図っています。
有償資金協力では、低利で返済期間の緩やかな条件を活かして、モンゴル国内の炭坑施設の改修およびスペアパーツ供与、火力発電所の継続的な改修、新空港の建設など大規模なインフラ整備事業を中心に様々な経済援助を実施してきました。また鉱業依存の経済体制を改善し、民間セクター主導による産業の多様化を図るため、モンゴルの中小企業に対する低金利・長期の融資を行うための円借款「中小企業育成・環境保全ツーステップローン」を2005年と2010年の2回に渡り総額80億円供与しました。更に最近では、モンゴルが必要とする産業人材を育成し、同国の工学系高等教育機関の機能を強化するために、有償資金協力によって「工学系高等教育支援計画(MJEED)」を実施し、日本への留学を通じた人材育成への支援を行っています。
このように日本政府は、モンゴルとの外交関係樹立から今日まで様々な分野での支援を実施しており、2021年度までの支援総額はおよそ3641.07億円に達しています。このような日本政府のモンゴルに対する一貫した支援により、民主化への移行期という財政的に最も苦しい時期に極めて大きな役割を果たすとともに、モンゴルの国造りを担う人材育成を行っています。
対モンゴルODA支援額(2022年11月時点)
| 年度 | 有償資金協力( 円借款) |
無償資金協力 | 技術協力 | 累計 |
| 1977~2021 | 1,829.44億円 | 1,254.34億円 | 557.29億円 | 3,641.07億円 |
注)・円借款は借款契約ベース、無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績ベースによる。
・出典)政府開発援助(ODA)国別データ集2022
2.支援方針
モンゴルの経済は鉱物資源の輸出に大きく依存しており、経済の多角化が課題となっています。また、堅実な財政再建を行い、今後、持続可能な経済成長を達成するためには、安定したマクロ経済運営の実現とともに、経済成長の恩恵を全国民が等しく享受するような政策運営が必要です。さらに、ウランバートル市への人口の一極集中による都市問題や地域格差が深刻化しています。モンゴル政府が経済発展を確実なものとするとともに、その恩恵を貧困層まで十分に波及させ、持続可能で均衡のとれた成長に向けたモンゴル政府の取組を我が国として支援するために、(1)健全なマクロ経済の実現に向けたガバナンス強化、(2)環境と調和した均衡ある経済成長の実現、(3)包摂的な社会の実現、の3点を支援の重点分野としています。
3. 今後の方向性
モンゴルに対する日本政府のODAは、無償資金協力、有償資金協力、技術協力に大別されます。
無償資金協力は、開発途上国が社会経済開発のために必要な資機材、設備の調達や学校などの建設に必要な資金を贈与するもので、比較的所得が低い開発途上国を対象に実施しています。日本政府は同無償資金協力の実施にあたって、世界銀行が示す基準を一つの参考にしていますが、近年のモンゴル経済の発展によって一人当たりのGNIは世銀の示す無償資金協力の実施基準を既に超えています。このため、日本政府による対モンゴル無償資金協力は今後減少する傾向にあり、これに代わって低利で返済期間の緩やかな条件で開発資金を融資する有償資金協力が主流となる見込みです。
現在、モンゴルが抱える問題は多岐に亘り、ODAだけでの解決は困難な状況にあります。2016年6月7日に日・モンゴル経済連携協定(EPA)が発効し、経済分野での二国関係は一層緊密化し、外国投資の増加、産業の多角化が期待されます。今後の対モンゴルODAにおいては、これら民間企業との連携も大いに期待されます。
また、技術協力は、日本の知識・技術・経験を活かし、モンゴルや地域の社会・経済の担い手となる人材の育成を目的に行う協力で、教育、保健、環境、農牧業など幅広い分野において日本の専門家とモンゴルの政府機関や専門家が協力してプロジェクトを進めています。また、両国の研究機関が協力して共同研究を行う、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)も技術協力に含まれ、モンゴルでは現在「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」及び「遊牧民伝承に基づくモンゴル草原植物資源の有効活用による草地回復プロジェクト」が実施中です。
無償資金協力は、開発途上国が社会経済開発のために必要な資機材、設備の調達や学校などの建設に必要な資金を贈与するもので、比較的所得が低い開発途上国を対象に実施しています。日本政府は同無償資金協力の実施にあたって、世界銀行が示す基準を一つの参考にしていますが、近年のモンゴル経済の発展によって一人当たりのGNIは世銀の示す無償資金協力の実施基準を既に超えています。このため、日本政府による対モンゴル無償資金協力は今後減少する傾向にあり、これに代わって低利で返済期間の緩やかな条件で開発資金を融資する有償資金協力が主流となる見込みです。
現在、モンゴルが抱える問題は多岐に亘り、ODAだけでの解決は困難な状況にあります。2016年6月7日に日・モンゴル経済連携協定(EPA)が発効し、経済分野での二国関係は一層緊密化し、外国投資の増加、産業の多角化が期待されます。今後の対モンゴルODAにおいては、これら民間企業との連携も大いに期待されます。
また、技術協力は、日本の知識・技術・経験を活かし、モンゴルや地域の社会・経済の担い手となる人材の育成を目的に行う協力で、教育、保健、環境、農牧業など幅広い分野において日本の専門家とモンゴルの政府機関や専門家が協力してプロジェクトを進めています。また、両国の研究機関が協力して共同研究を行う、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)も技術協力に含まれ、モンゴルでは現在「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」及び「遊牧民伝承に基づくモンゴル草原植物資源の有効活用による草地回復プロジェクト」が実施中です。